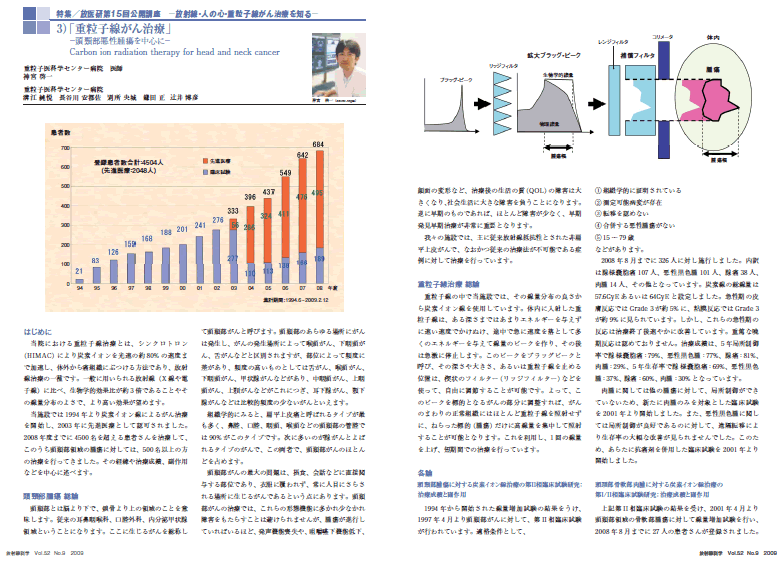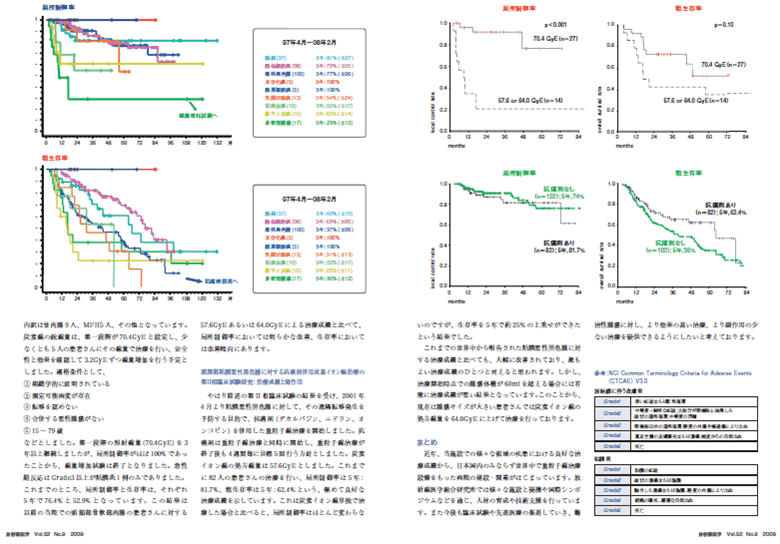留学報告
重粒子医科学センター留学記
神宮 啓一
2008年4月~
2008年4月より千葉の放射線医学総合研究所の重粒子医科学センターに留学してきましたので、報告致します。留学とはいってもスタッフとして日常診療を行っておりました。
重粒子センターでは、医師・歯科医師15名程度で100床の病院を診ております。それぞれ頭頸部、骨軟部、肺、消化器、婦人科、前立腺にグループ化されておりました。私は当時病院長であった溝江先生の下、頭頸部グループに所属しました。この頭頸部グループは溝江先生を除くとMDがいないとのことで、こちらのグループ所属となりました。毎週ある症例検討会や倫理委員会を全例通さないと治療が開始できないため、毎日書類の作成を夜中に行うのが日課でした。日中は外来と重粒子線治療室での位置確認や固定具作成、CTシミュレーションを行うルーチンワークがあるため、夕方から放射線治療計画を始めるのです。治療計画は、これまで学んできたX線の治療計画とは比べものにならない緻密なもので、1例に2~3日費やすような感じでした。この理由は、X線と違い線量勾配が極めて急峻である(lateralもdistalも)ため、しっかりとしたtargetをしないと、低線領域がすぐにできてしまうためです。頭頸部グループでは1~2日毎に1例の症例登録されるのですが、病院長は手を出さず出来てくる線量分布を確認し、文句を言うことに徹しており、また同僚のひとりは病気にかかってしまい、通常業務もできないような状態となったため、ほぼ2人でこの仕事をこなして行くこととなりました。もちろんもう一人の働き手も私の上司にあたるため、仕事をおねがいすることはできず、一人黙々と仕事をやっておりました。一時は鬱になるかと思ったくらいに疲れ果てる毎日でした。また重粒子センターでは半年に一度、院外のドクターに臨床試験の進捗状況を報告する会議が各グループで行われるため、そのデータのupdateなどもなかなか苦労をしました。時々、同僚達と飲みに出かけたりするのが楽しみで、月島のもんじゃを食べ歩いたり、大相撲を砂かぶり席で観戦したりすることができました。しかし、そんな中でも自分の研究を行わなければならず、いただいたテーマは頭頸部原発の骨軟部肉腫の重粒子線治療 線量増加試験成績をまとめることでした。これは比較的明瞭な結果が出ておりましたので、すぐにデータがまとまり、2008年の秋の北日本地方会ではその結果を発表することができ、論文化しました。しかし、この線量増加試験を行った理由が、その以前に行われた第2相試験の結果を受けて、肉腫の治療成績が悪いことからおこなっており、その第2相試験の結果を公表するまで投稿は待ってくれとのことでした。ところが、その第2相試験結果の報告がなされず、次第にじれてきてしまい、ついに辻井理事と相談の上、投稿を行うこととなりました。といっても、今度は辻井理事からの納得がなかなか得られず、結局投稿したのは、仙台に戻る日がせまった2010年4月でした。いただいたテーマだけではつまらなかったので、自分でも研究テーマを考えてみることにしました。我々、頭頸部グループの扱う疾患で多いのが、粘膜悪性黒色腫と腺様嚢胞癌でした。ともに珍しい疾患であり、X線治療では根治することが困難といわれる疾患でした。腺様嚢胞癌に対する重粒子線治療における照射野設定についての研究も行い、2009年のJASTRO総会で発表いたしました。しかし、なかなか明瞭な結果がでませんでしたの、論文にはせずにお蔵入りとしました。つぎに粘膜悪性黒色腫では遠隔転移の発生が高頻度であるため、なかなか局所治療だけではうまく行かず、化学療法併用にて重粒子線治療が行われておりました。それにも関わらず、遠隔転移の発生が依然として問題となっておりました。そのことから、遠隔転移の予測因子を探そうと考えました。頭頸部グループの症例で、治療前に必ず撮像しているMRIやメチオニンPETの所見に注目しました。メチオニンPETのT/M比や拡散強調像から得られるADC値により予後解析を行うこととしました。この研究は日医放と放医研から研究助成をいただき、リッチな研究を行うことができました。そのおかげで、頭頸部の粘膜悪性黒色腫では症例数の多い40例程度で検討ができました。1年目の研究にて、メチオニンPETのT/M比よりもminimum ADC値(おそらくは腫瘍密度あるいは腫瘍増殖能をみている)の方が予後との相関が強かったことから、2年目からはADC値のみに着目しました。その結果、minimum ADC値の低い群では、遠隔転移の発生率が有意に高いことが分かりました。そのため、生命予後についても有意差がでてきましたので、論文化しました。

さて、頭頸部グループのボスであった溝江先生からある日突然に、イタリアの重粒子線施設に赴任することになったということを、2ヶ月前に告げられました。日常診療にはそれほど支障はなかったのですが、あまりの突然さにビックリしました。それでも私を信用してくれたのかどうかはわかりませんが、外来なども赴任当初から任せてくれて、貴重な症例をたくさん拝見させていただき、私の放射線科腫瘍医としての大きな財産になっております。忘れられない症例なども沢山経験させていただき、大変感謝しております。研究成果としては、2年間でIJROBPとROより1編ずつの原著論文、ASTROやPTCOGといった国際学会での発表、脳外科医向けの教科書を1編、また症例報告を1編投稿中です。その他、重粒子医科学センターでは世界の粒子線施設とシンポジウムを頻回におこなっており、中国・蘭州では口頭発表もさせていただき、英語の勉強にもなりました。放医研に行く前から通っている週1回の駅前留学は現在も継続中ですが、なかなか上達が見られず、出張先への車の中でも英会話のCDを聞くようになってしまいました。
さらには今後重粒子線治療施設を建設しようとしている地域の一般市民への講演のために地方まで出かけたり、なかなか出来ない経験をさせていただきました。
最後に、このような貴重な機会を与えてくださった、山田章吾教授を初め、医局の先生方にお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。